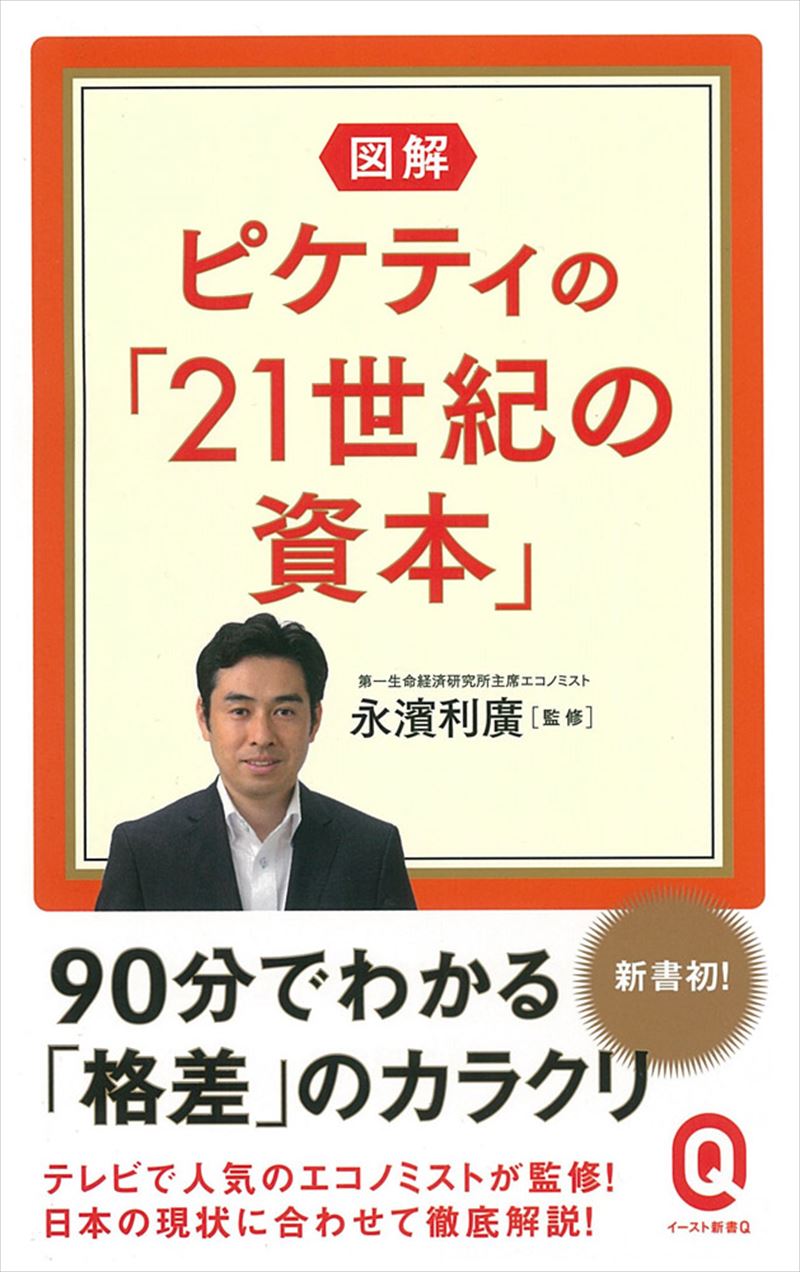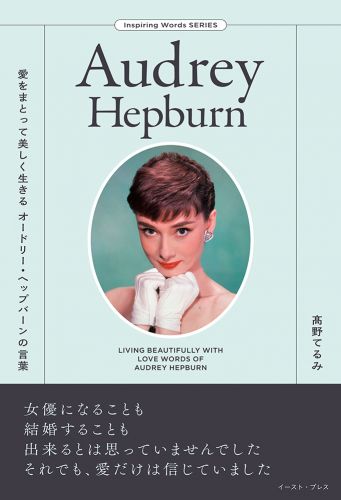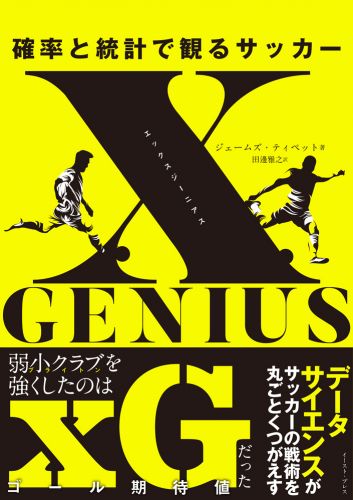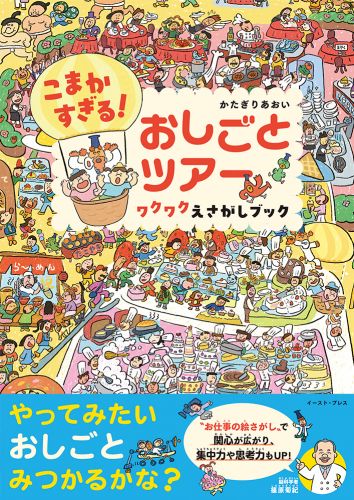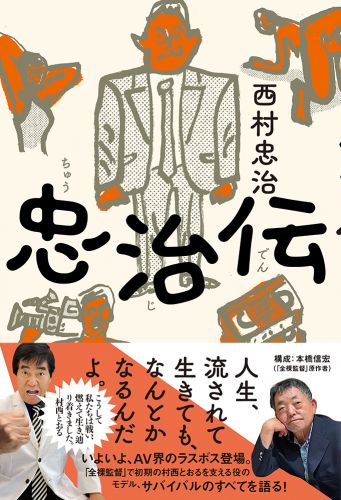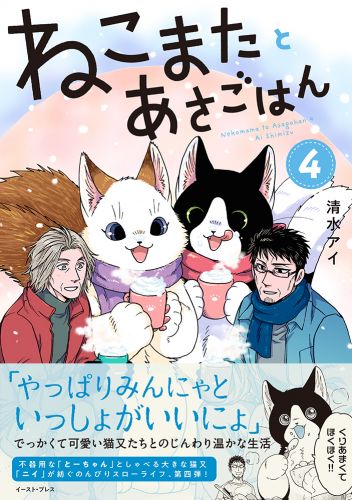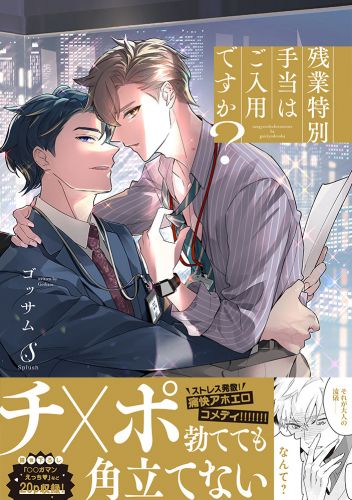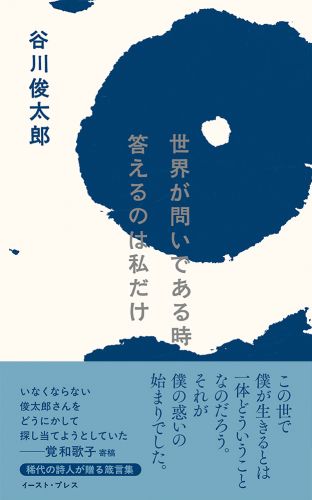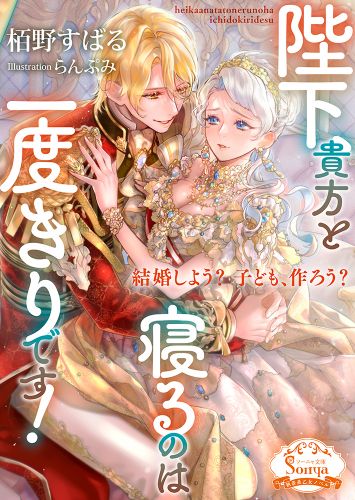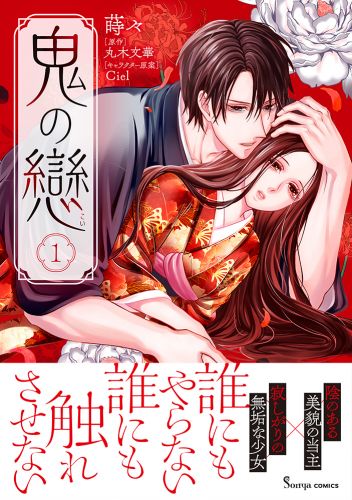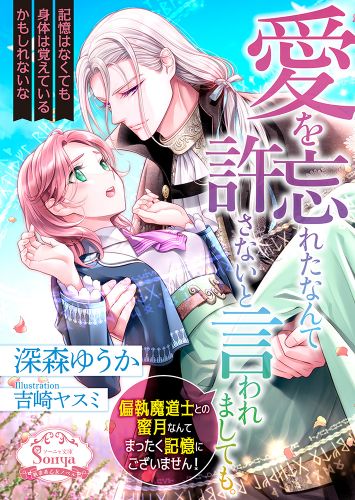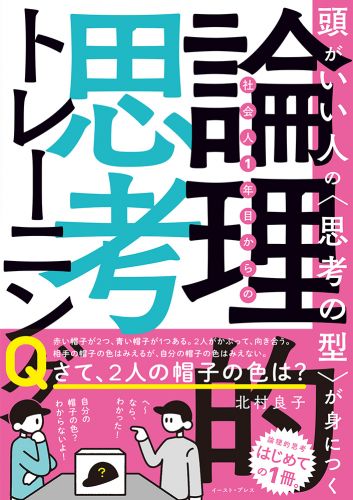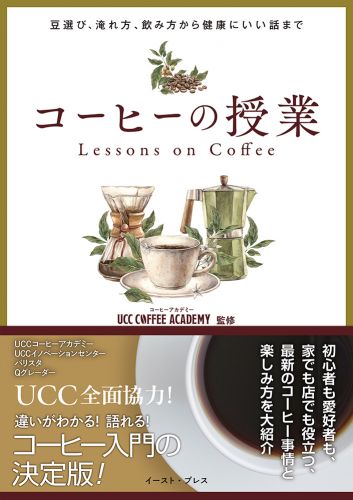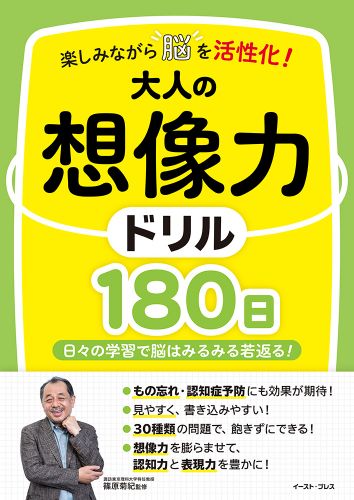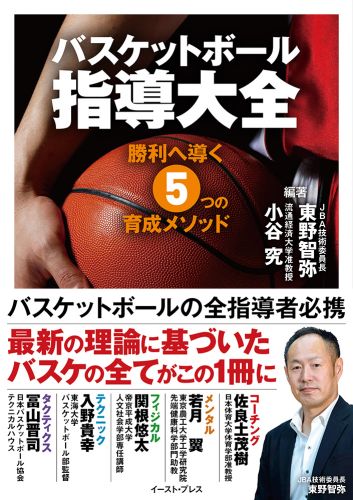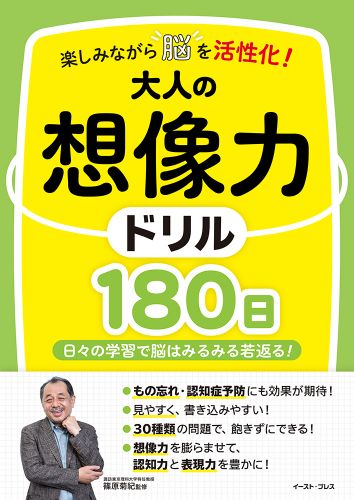図解 ピケティの「21世紀の資本」
90分でわかる「格差」のカラクリ。
テレビで人気のエコノミストが監修! 日本の現状に合わせて徹底解説!
- 定価
- 880円(本体800円+税10%)
- ISBN
- 9784781680040
- JANコード
- 1920230008005
- NDC分類
- 331
- 発売日
- 2015年5月8日
- 判型
- 新書判
- 製本
- 並
- ページ数
- 192ページ
- カテゴリー
-
ビジネス・経済
詳細Detail
- 内容紹介
- 目次
日本版が2014年暮れに発売された『21世紀の資本』は、その解説本も数多く出版されているが、一部をピックアップしただけの本や、ピケティの名前を利用して自分の理論を世にアピールしようとする本が多く、全体を解説した本はほとんどない。そのような観点から、本書では原著に忠実に全体を解説した。あわせて、日本における格差問題やアベノミクスの評価について独自の解説を加えた。
永濱利廣(ながはま・としひろ)
第一生命経済研究所主席エコノミスト。1995年早稲田大学理工学部卒業、2005年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。95年4月第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社。98年4月より社団法人(現・公益社団法人)日本経済研究センター出向等を経て、08年4月より現職。一橋大学非常勤講師、跡見学園女子大学非常勤講師、景気循環学会理事など。
永濱利廣(ながはま・としひろ)
第一生命経済研究所主席エコノミスト。1995年早稲田大学理工学部卒業、2005年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。95年4月第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社。98年4月より社団法人(現・公益社団法人)日本経済研究センター出向等を経て、08年4月より現職。一橋大学非常勤講師、跡見学園女子大学非常勤講師、景気循環学会理事など。
はじめに 原著を忠実に読み解けば、日本経済の未来も見えてくる 永濱利廣
序章 日本人はピケティから何を学ぶべきか
―永濱利廣が教える「r∨g」の本当の意味
3ページでわかる「r∨g」の法則
ピケティ理論は「アベノミクス批判」なのか
「超格差社会」で資産を守る方法
第1章 ピケティが考える「資本主義」のカラクリ
―90分でわかる『21世紀の資本』①
ピケティの「資本主義の基本原則①」
「資本/所得比率」の変化に着目する
世界経済における「格差」の歴史
解消しつつある富裕国と貧困国の格差
人口が増えれば格差は縮小する
経済成長データを「超長期」で読み解く
経済成長とインフレ・デフレのメカニズム
二つの「釣り鐘型曲線」から見えてくるもの
第2章 ピケティが考える「資本」のカラクリ
―90分でわかる『21世紀の資本』②
1970年までの欧米各国の資本の変化
二度にわたって「資本/所得比率」が減少した理由
ピケティの「資本主義の基本原則②」
「貯蓄率」と「成長率」に着目する
1970年以降の欧米各国の資本の変化
二つの世界大戦の影響はこうして克服した
成長が鈍れば格差は拡大する
資本と所得の分配から見えてくる事実
第3章 なぜ「資本」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』③
労働の格差と資本の格差の違いとは
労働所得より大きい資本所有の格差
格差を決定づけた歴史の転換期
「超世襲社会」と「超能力主義社会」が格差を生む
欧米に見る資本格差の歴史
「勝ち組」になったのはどんな人々か
「超格差社会」アメリカの現状
1%の人数で20%の所得を占める人々の正体
第4章 なぜ「所得」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』④
あなたの給料はどうやって決まるのか
「最低賃金」が格差の大きさを決める
なぜアメリカで「超格差社会」が発生したのか
自分の給料の決定権を持つ経営者の優位性
欧米に見る所得格差の歴史
ヨーロッパと日本の格差がアメリカより小さい理由
新興国における格差のメカニズム
なぜ先進国より深刻で把握が難しいのか
第5章 なぜ「持てる者」と「持たざる者」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑤
富の集中はいつから始まったのか
「世襲中流階級」が国富の3分の1を所有した19世紀
「r∨g」は論理的必然ではなく歴史的事実
成長率が資本収益率より高い時代はめずらしかった
21世紀は19世紀ほどの格差社会にはならない
なぜ「r」と「g」の差は縮小しつつあるのか
「貯蓄」より「相続」が有利になるカラクリ
高齢化社会も格差拡大の原因となる
増大する「相続」にどう対応すべきか
相続財産が民間財産の3分の2という現実
世界が不労所得生活者だらけになる日
1970年代以降は生涯総資産の4分の1が相続になる
第6章 なぜ「持てる者」がさらに儲かる社会になるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑥
ピケティ理論の肝「資本収益率」の格差とは
資産が大きいほど収益率は高くなる
世界は誰の手によって「所有」されるのか
新興国の成長はキャッチアップした時点で止まる
第7章 「格差社会」に特効薬はあるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑦
社会保障と税金の関係
国家は君主的役割に徹するべきか、福祉に力を入れるべきか
累進課税は本当に格差解消に効果的なのか
「最高税率」が格差の大きさを決める
資本税の導入に立ちはだかる「壁」
「隠蔽された資本」をあぶり出す方法とは
「国の借金」はどうなるのか
インフレ政策で公的債務は削減できる
第8章 日本経済の「格差」のカラクリ
―ピケティ理論で読み解くアベノミクス①
戦後日本の「格差」の歴史
「1億総中流時代」は幻想だったのか
なぜ「非正規雇用」が激増したのか
4割を占める彼らを救う方法とは
「教育格差」が「経済格差」を招くカラクリ
「持たざる者」が絶対に這い上がれない社会の到来
なぜ「世代間格差」はなくならないのか
生涯所得の半分が高齢者のために消えていく時代
第9章 日本の「格差社会」を解消する処方箋
―ピケティ理論で読み解くアベノミクス②
「アベノミクスで格差が広がる」のウソ
パイの拡大と雇用流動化で格差は解消する
アベノミクスにひそむ問題点
円安への対応、「安定志向」の解消がネック
アベノミクス「第3の矢」への期待
人口増加、雇用流動化、地方創生、農業自由化の効果とは
「デフレ脱却で経済成長」は本当か
最終目標は財政健全化と社会保障の効率化にあり
参考文献
序章 日本人はピケティから何を学ぶべきか
―永濱利廣が教える「r∨g」の本当の意味
3ページでわかる「r∨g」の法則
ピケティ理論は「アベノミクス批判」なのか
「超格差社会」で資産を守る方法
第1章 ピケティが考える「資本主義」のカラクリ
―90分でわかる『21世紀の資本』①
ピケティの「資本主義の基本原則①」
「資本/所得比率」の変化に着目する
世界経済における「格差」の歴史
解消しつつある富裕国と貧困国の格差
人口が増えれば格差は縮小する
経済成長データを「超長期」で読み解く
経済成長とインフレ・デフレのメカニズム
二つの「釣り鐘型曲線」から見えてくるもの
第2章 ピケティが考える「資本」のカラクリ
―90分でわかる『21世紀の資本』②
1970年までの欧米各国の資本の変化
二度にわたって「資本/所得比率」が減少した理由
ピケティの「資本主義の基本原則②」
「貯蓄率」と「成長率」に着目する
1970年以降の欧米各国の資本の変化
二つの世界大戦の影響はこうして克服した
成長が鈍れば格差は拡大する
資本と所得の分配から見えてくる事実
第3章 なぜ「資本」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』③
労働の格差と資本の格差の違いとは
労働所得より大きい資本所有の格差
格差を決定づけた歴史の転換期
「超世襲社会」と「超能力主義社会」が格差を生む
欧米に見る資本格差の歴史
「勝ち組」になったのはどんな人々か
「超格差社会」アメリカの現状
1%の人数で20%の所得を占める人々の正体
第4章 なぜ「所得」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』④
あなたの給料はどうやって決まるのか
「最低賃金」が格差の大きさを決める
なぜアメリカで「超格差社会」が発生したのか
自分の給料の決定権を持つ経営者の優位性
欧米に見る所得格差の歴史
ヨーロッパと日本の格差がアメリカより小さい理由
新興国における格差のメカニズム
なぜ先進国より深刻で把握が難しいのか
第5章 なぜ「持てる者」と「持たざる者」の格差は生まれるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑤
富の集中はいつから始まったのか
「世襲中流階級」が国富の3分の1を所有した19世紀
「r∨g」は論理的必然ではなく歴史的事実
成長率が資本収益率より高い時代はめずらしかった
21世紀は19世紀ほどの格差社会にはならない
なぜ「r」と「g」の差は縮小しつつあるのか
「貯蓄」より「相続」が有利になるカラクリ
高齢化社会も格差拡大の原因となる
増大する「相続」にどう対応すべきか
相続財産が民間財産の3分の2という現実
世界が不労所得生活者だらけになる日
1970年代以降は生涯総資産の4分の1が相続になる
第6章 なぜ「持てる者」がさらに儲かる社会になるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑥
ピケティ理論の肝「資本収益率」の格差とは
資産が大きいほど収益率は高くなる
世界は誰の手によって「所有」されるのか
新興国の成長はキャッチアップした時点で止まる
第7章 「格差社会」に特効薬はあるのか
―90分でわかる『21世紀の資本』⑦
社会保障と税金の関係
国家は君主的役割に徹するべきか、福祉に力を入れるべきか
累進課税は本当に格差解消に効果的なのか
「最高税率」が格差の大きさを決める
資本税の導入に立ちはだかる「壁」
「隠蔽された資本」をあぶり出す方法とは
「国の借金」はどうなるのか
インフレ政策で公的債務は削減できる
第8章 日本経済の「格差」のカラクリ
―ピケティ理論で読み解くアベノミクス①
戦後日本の「格差」の歴史
「1億総中流時代」は幻想だったのか
なぜ「非正規雇用」が激増したのか
4割を占める彼らを救う方法とは
「教育格差」が「経済格差」を招くカラクリ
「持たざる者」が絶対に這い上がれない社会の到来
なぜ「世代間格差」はなくならないのか
生涯所得の半分が高齢者のために消えていく時代
第9章 日本の「格差社会」を解消する処方箋
―ピケティ理論で読み解くアベノミクス②
「アベノミクスで格差が広がる」のウソ
パイの拡大と雇用流動化で格差は解消する
アベノミクスにひそむ問題点
円安への対応、「安定志向」の解消がネック
アベノミクス「第3の矢」への期待
人口増加、雇用流動化、地方創生、農業自由化の効果とは
「デフレ脱却で経済成長」は本当か
最終目標は財政健全化と社会保障の効率化にあり
参考文献